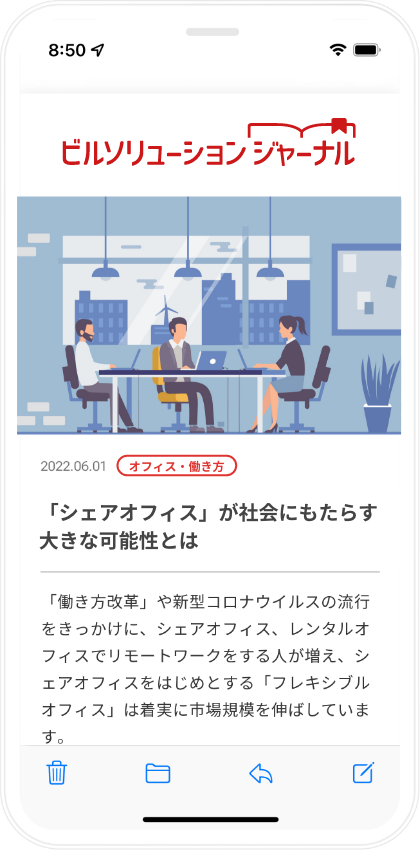ビルの給排水設備に関しては、建築基準法・ビル管理法・浄化槽法による規制が適用されます。ビルオーナーは、これらの法律の規定に従い、給排水設備の整備や点検を行わなければなりません。
今回はビルの給排水設備を規制する3つの法律について、ビルオーナーが注意すべきポイントをまとめました。
ビルの給排水設備に関係する法律
ビルの給排水設備の整備・点検については、主に以下の3つの法律が適用されます。
(1) 建築基準法
(2) ビル管理法(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)
(3) 浄化槽法
(1) 建築基準法による給排水設備の規制
建築基準法では、一定規模以上の建築物や、都市計画区域・準都市計画区域・準景観地区などにおける建築物につき、敷地・構造・設備・用途に関する基準が定められています。
建築基準法上、給排水設備は「建築設備」として規制の対象となっています(同法2条3号)。
たとえば給排水設備を含む建築設備は、建築確認および完了検査の対象です(同法6条、7条)。
建築物における給排水設備の設置・構造に関する基準は、建築基準法施行令129条の2の4で定められています。*1
同基準を満たさなければ建築確認がなされず、完了検査にも通りません。
また、建築基準法施行令16条で定められる安全上・防火上・衛生上特に重要な建築物については、給排水設備を含む建築設備につき、毎年1回建築士等に調査をさせて、その結果を特定行政庁へ報告しなければなりません(建築基準法12条)。
ビルについては、その多くが建築設備の調査・報告義務の対象となりますので、給排水設備についても定期調査を行う必要があります。
(2) ビル管理法による給排水設備の規制
オフィスや店舗が入居するビルのうち、延べ面積が3,000㎡以上のものは、ビル管理法に基づく「特定建築物」に該当します(ビル管理法2条、ビル管理法施行令1条)。
特定建築物であるビルについては、「建築物環境衛生管理基準」*2 に従って維持管理をしなければなりません(ビル管理法4条1項、ビル管理法施行令2条)。
ビルの維持管理義務を負うのは、実質的に見て適切に特定建築物を維持管理すべき立場にある者(=特定建築物維持管理権原者)です。
(例)所有者、一棟借りの賃借人、ビルの維持管理業務を全面的に受託している管理業者など
建築物環境衛生管理基準では、給水の管理と排水の管理について、それぞれ遵守すべき基準が定められています。
- 給水の管理
(a) 飲料水の管理
水道法の水質基準に適合する水を供給するほか、厚生労働大臣が定める「空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準」*3 に従い、飲料水に関する設備を適切に維持管理することが求められます。
(b) 飲料水の水質検査について
6か月・1年・3年ごとに、所定の検査項目について水質検査を実施することが求められます。
(c) 雑用水の管理
雑用水(散水・修景・清掃・水洗便所の用に供する水)として雨水・下水処理水等を使用する場合は、所定の衛生上必要な措置を行った上で供給しなければなりません。 - 排水の管理
汚水等の漏出等が生じないように、設備の補修・掃除を行わなければなりません。排水設備の清掃頻度は、6か月以内ごとに1回とされています。
そのほか、厚生労働大臣が定める「空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準」*3 に従い、排水設備を適切に維持管理しなければなりません。
建築物環境衛生管理基準に従って給排水設備を適切に維持管理していない場合は、都道府県知事による改善命令等の対象となるので注意が必要です(ビル管理法12条)。
(3) 浄化槽法による給排水設備の規制
一般家庭に比べて排水量が多く、地階などでは下水道を通じた直接の排水が困難な場合があるため、ビルには浄化槽が設けられるのが一般的です。
浄化槽には、ビル全体から排出されたし尿や雑配水が集められ、浄化措置が施されます。その後、排水ポンプを通じて下水道本管へ流します。
浄化槽管理者は、浄化槽法の規制を遵守しなければなりません。浄化槽法による主な規制内容は、以下のとおりです。
※「浄化槽法」に関する詳細は、以下の記事をご覧ください。
参考記事:ビルオーナーが注意すべき「浄化槽法」 規制の概要やチェックポイントを解説
- 浄化槽の設置等の届出
浄化槽を設置し、またはその構造・規模を変更しようとする者は、都道府県知事および環境省・国土交通省への届出を行わなければなりません(浄化槽法5条1項)。
※環境省・国土交通省への届出は、都道府県知事を経由して行います。 - 浄化槽の水質検査
浄化槽を新規に設置し、または規模・構造の変更がなされた場合は、3か月経過後から5か月以内に水質検査を受けなければなりません(浄化槽法7条1項)。
その後は原則として毎年1回以上、水質の定期検査を受ける必要があります(浄化槽法11条1項)。 - 浄化槽の保守点検
毎年1回以上(全ばっ気方式の浄化槽については、おおむね6か月ごとに1回以上)、浄化槽の保守点検を実施しなければなりません(浄化槽法10条1項本文、環境省関係浄化槽法施行規則7条)。
浄化槽の保守点検は、環境省関係浄化槽法施行規則2条に定められる「浄化槽の保守点検の技術上の基準」に従って行うことが求められます。 - 浄化槽の清掃
毎年1回以上(全ばっ気方式の浄化槽については、おおむね6か月ごとに1回以上)、浄化槽の清掃を実施する必要があります(浄化槽法10条1項本文、環境省関係浄化槽法施行規則7条)。
浄化槽の清掃は、環境省関係浄化槽法施行規則3条に定められる「浄化槽の清掃の技術上の基準」に従って行うことが求められます。 - 浄化槽に関する技術管理者の設置
処理対象人員が501人以上の浄化槽について、管理者は自ら管理する場合を除き、技術管理者の設置が義務付けられています(浄化槽法10条2項、浄化槽法施行令1条)。 - 都道府県知事に対する各種報告
浄化槽の使用開始・処理対象人員が501人以上の浄化槽に係る技術管理者の変更・浄化槽管理者の変更が発生した場合には、各事由の発生日から30日以内に、都道府県知事に報告書を提出しなければなりません(浄化槽法10条の2)。 - 浄化槽使用の廃止の届出
浄化槽の使用を廃止した場合には、廃止日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出る必要があります(浄化槽法11条の3)。
特に、浄化槽法に基づく浄化槽の保守点検・清掃を適切に行わない場合、都道府県知事による改善措置命令・使用停止命令などの対象になり得るのでご注意ください(浄化槽法12条2項)。
まとめ
ビルの給排水設備については、各法令により整備・点検が義務付けられています。法令によるビル設備の規制は技術的・専門的なものが多く、そのすべてをビルオーナーが自ら把握することは非常に大変です。
給排水設備の整備・点検を含めて、ビルの維持管理に関するルールを適切に遵守するためには、ビル管理会社や建築士などの技術専門家に相談して、アドバイスを求めることをおすすめします。
- MAIL MAGAZINE
-
ビルに関わるすべての方に!ちょっと役に立つ情報を配信中
メール登録
*1
e-gov法令検索「建築基準法施行令」
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325CO0000000338
*2
厚生労働省「建築物衛生管理基準について」
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/seikatsu-eisei10/
*3
厚生労働省「空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準」
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/seikatsu-eisei10/01.html